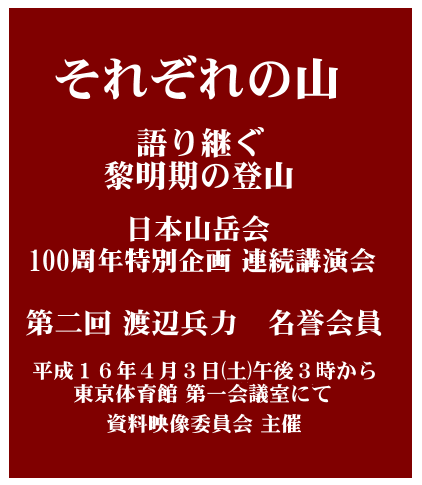

90歳とは思えぬ姿
「山への想い・山に残した足音」
── 私と山との間柄 ──
人間と山とのかかわり方は、年とともに変るものであろうが、若い時に育った「山への想い」はそう変るものではない
満席の中での映画会 山との出会い
私が、初めて山と出会ったのは、7歳の時 (大正10年・1921年) である。父が友人を訪問する旅に私を同行した。その友人は木曽御料林の管理責任者であった。森林鉄道に乗せてもらって、どこか山間部につれていかれた。そして、高く大きい檜の木立の間から、雲をまとった、雨上がりの木曽御岳の姿を見た。とても美しかったことを、ほんとうにかすかに覚えている。これが都会育ちの少年であった私の心に、山が入ってきた最初であった。 大正13 (1924) 年、成蹊学園小学校2年生の夏、父に連れられて富士山に登った。吉田口から登り、5合目小屋で1泊し、御殿場口に下山した。80年後の今日、かすかに覚えているのは、すっかり日が落ちて暗くなった道を、父と子がトボトボと歩いている光景である。これが、登山という行為を経験した最初であり、その山は、たまたま日本列島で一番高い富士山だった。
今なお健在な「虹芝寮」
私が成蹊学園在学中に学制が変わり、新制の7年生高校が設置された。その結果、同じ学園で14年間を過ごし、移転は大学だけという恵まれた状況で学徒生活を送ることになった。この事実は、「山」と緑のある生涯を送ったことにおおいに関与しているように思う。 成蹊学園在学の昭和6 (1931) 年、山仲間の間で 「山小舎が欲しい!」 という望みがでて、上越国境の谷川岳の東側に適地を探し、山小舎を建築することになった。それが70年後の今日まで同じ場所に健在な 「虹芝寮」 である。この山小舎の適地探しや、小舎作りに関する諸々の手続き、そしてでき上がった小舎での生活や保全の仕事など……。いずれも、それまでやってきた単なる登山とは違う思いと目で山を見て、そして考えていかねばならないという、側面との付き合いがあった。母校の校長の・「金は出してやるが口は出さない」 というひと言が、我々青少年をひどく苦しめたが、実にすばらしい教育であり、非常に面白い経験だったと、今になって思い浮かべるのである。 しかし、山小舎を維持することの方がはるかに困難であり、ひとつの小舎を今日まで維持してきた成蹊大学の山好きの後輩たちに、 心から感謝したいと思う。
スキー事始め
私の父は、秩父宮家ができた時から御用掛として宮家に奉仕していたので、殿下が初めてスキーをなさった時 (大正11年・1922年)、細川護立さんの赤倉の別荘地にお供をした。その時にスキーを初めて経験した父は、なかなか面白いものだということで、直ちに私にスキーを買ってやろうと言った。そして探したが、子供用のスキーはどこにも売ってなかった。それで、作ることになったが、どうせだんだん大きくなるだろうといって、いくら手を伸ばしても先がつかめないぐらい大きなスキーと靴を作らせたのだった。そして、それを持って五色にお供をさせられたのである。初めて見る真っ白な吾妻の山は美しいと思ったが、スキーの履き方だけを教わって、鉢森山の麓でこ一行の下山をじ-つと待っていた辛く苦しい思い出は今も忘れられない。
自然から……「自力で学びとる」
私は山とスキーの存在を父から教わったが、どうして山に登るのか、どうしてスキーで滑れるのかということは全く教わらなかった。父は、同時に始めた私に教える腕前を持っていなかったのである。それで、山やスキーについて、自分で自然から学びとらなければならなかった。そして、一言居士流に言えば、自然から教わるのが最も自然で正当であると妄信していた。大学では、新しい仲間と一緒に山に登りスキーもしたが、少しも引けをとらないと自負していた。小さい頃から山やスキーを始め、自力で、山と、雪と、風から学び、それに対応してきた。そのことが今思えば、得意だった気がする。しかし、その仲間たちが 「世の中」 について、私の知らないことをいっぱい知っているのには仰天した。私は 「山」 しか知らない都会の坊ちゃんだったらしい。
登山の屁理屈
山登りには理屈がつきものであるということを、山の本で読んだ。本には 「山を想う」 という記事が多く、その方法論は、経済学や社会学で学んだように、静態的な均衡状態を山と人間との間に設定していた。山をこのように考えているのだ、こんないい山があるのだという話はあるが、学ぼうとしている技術については、十分な言葉で書いていないと感じた。なぜかと考えたとき、山登りの技術とは、「技術」と「作法」、つまり 「技法」 ではないかと思うようになった。この両方をわきまえなければ、正しい登山はできないのではないかと…。 ところが、作法というのは全部人間が作ったものであって、山が作った作法はない。山登りとはそんなものだったろうかと考えた。そしたら、問題にぶちあたった。今まで私のやってきた山登りは、どうだったのだろうかと……。 成蹊学園時代 (昭和8年・1933年) に高木君と谷川に登ったのは、当時ドイツの学生だったシュミット兄弟がマッターホルンの北壁を初登頂した直後だった。その記事が雑誌に載っていた。その真似をやっただけで、決して大したことじやない。非常に純朴なる学生であったともいえるが、流行の先端を真似て、岩登りをやったのではなかったかと…。
二つの「知」の併存
成蹊学園在学の15歳の春休みに、後立山の五竜と白馬を雪のある間に登ろうという話になった。高木君と2人で細野部落の大谷定雄という人夫を雇い、唐松の小屋に入った。その時、大谷が剣の方を眺めて 「剣にあの雲ができたら、2時間後に後立山は猛吹雪になる。吹雪が来る前に五竜へ行きましょう」 と言った。その時、唐松の周辺にはまだ青空が見えていたが、確かに黒部川の谷間を越えた剣には雲がかかっていた。慌ててピッケルとアイゼンを持ち、半分駆け足で五竜を往復し、帰途は牛首の辺りで体が舞いそうな猛吹雪にあったが、無事に小屋に戻った。あの時大谷が、2時間後の後立山の猛吹雪を予見できたのは、麓で農耕をしていた農民こその知識ではないかと思う。彼らは、白馬の麓で米を作って生きていたから、自然を肌で感じる知り方をしていたように思う。一方の知識は、学校や本で学ぶものだが、どちらの知り方も正しいのだと思う。知識には、自然から教わるものと、人から教わるものとの両方があるようだ。遊びや、余技としての山やスキーでは、人から教わるのではなくて自然から教わる、自然にそうなってきたように思われる。
「雪線」へのこだわり
戦前に私が盛んに登っていた日本列島の山々は、所詮、雪線のない山であった。だが、山登りの本の主役は、雪線以上の山や氷河のあるスイスの山々であった。雪線以下の山しかない国に住む私は、雪線以上の岩や氷の世界の山登りを求めていたのかもしれない。今日、外国の山で雪線の上下など考える人はいないと思う。しかし、我々の時代、山登りをする者にとっては、なかなか重要な問題であった。山々の状態が違うだけでなく、生活する人々の生態にも大きな相違があろう。極地の雪線は海の中にある。カラコルムもチョモランマも雪線を越える領域の登山であった。雪線を越えると氷河がある。その氷河の上にまた岩があり、氷河の固い雪と、それから岩と、両方を登ったり下りたりしなければならない。
それがヒマラヤの山登りだ。ところが、日本には雪線以上の山はないから、やったことがない。その雪線を解決するのは、お金のようで、どうもその辺りで昔と今の登山が違いだしたと感じている。
「集団的自由」の存在
それまで私がやってきた山登りとは、自由なスポーツであると思ってきた。その自由とは勝手気儘というものではなく、その山のある場所の掟を守るというものである。そして 「どこの山に、どのように登るか」 を決める自由は個人にあると思っていた。南極やヒマラヤの遠征では 「隊」 を形成して国から出て行く。そこには個人の自由は存在しないものと了解していた。ところが、3つの海外遠征で「集団の自由」 を体験した。その典型が南極観測隊であった。多くの人々が集まり、力を出しきって基地を拓き建設し、越冬した。この事実に接し、「集団の自由」と「個人の自由」 の存在と、その必要性を痛感した。
「登山考」と「責任の認識」
「山登り」 はスタティック (静態的) ではなく、山も動いているし、登る人間の方も動いている。だからむしろダイナミック (動態的)な関係にあって、それがちょうど釣り合っている時に安全な山登りができて、壊れた時に遭難をする。この関係を 「あいだがら」 と表現し、私の登山考としてきた。同時に、登山は本人の責任の問題であり、他人が責任を負うべきものではないと思っている。自分の遭難をリーダーのせいにするようなことは、もっとも山登りを知らない人のいうセリフである。しかし昨今の状況をみると、リーダーや添乗員が悪いといって、裁判沙汰になるということが日本以外でも起こっている。山登りの責任者というのは一体誰なのかという問題になり、登山における責任の認識が必要になってくる。他のスポーツでも同じようなことはあるかもしれない。日本山岳会は幸いにして、今まで大きな問題はおきていない。しかし、今後はこの問題に対しての考え方というものをだし、触れることが必要で、それが世の中のためにもなるのではないかと思っている。
今、思うこと
登山やスキーのできない年齢になった今、思うことがある。それは白馬や穂高の山案内人たちが、自然から肌で感じ知ったその知識を無にしてはいけないということである。それは説明することができない「知」 である。だからこそ、その「知」 に接し、経験することのない人たちに、何とかして伝え残すことが大きな課題であると思う。もし、科学だけが正しくて、科学以外のものは正しくないという雰囲気が日本山岳会の中にあるとすれば、それはいかがなものか。自然の移り変わり、その物語っているものを肌で感じ取らなければ生きていけないのである。その知識を、余技の中にどのように取り入れ、役立てていくかで、山での危険が少なくなるのではないかと、90歳になろうとする今、やっと気がついたところである。
【平成16年4月3日、東京体育館 (参加者120名) で行われた講演会記録を元に編集】(奈良 千佐子)
「山への想い・山に残した足音」
── 私と山との間柄 ──
人間と山とのかかわり方は、年とともに変るものであろうが、若い時に育った「山への想い」はそう変るものではない
* 渡辺兵力 プロフィール:
中国でも教鞭をとった農学博士。初期の南極観測隊員。1980年日本山岳会のチョモランマ登山の隊長。著書に「山旅の足音」名渓堂S60年登山のみならずスキーに造詣が深い。羽に衣を着せぬ発言は、思慮深い正論として山岳会内でも支持者が多い。若い会員が少ないといわれている山岳会においてなおかつ若い人達に人気の高い貴重な存在である。
1914年(大正 3) 東京に生れる
1922年(大正11) 山形県五色温泉付近でスキーをはじめる
1935年(昭和10) 成蹊学園卒
1938年(昭和13) 東京大学農学部農業経済学科卒
1946年~53年(昭和21~28) 財団法人 日本農業研究所勤務
1953年~75年(昭和28~50) 農林省農業総合研究所勤務
1976年~84年(昭和50~59) 日本大学農獣医学部勤務
【山 歴】
1924年(大正13) 富士登山を最初として成蹊学園在学中に登山とスキーを学ぶ
1933年(昭和 8) 谷川岳一ノ倉奥壁積雪期初登攀
1935年(昭和10) 千島列島国後島チャチャ・ヌプリ冬季初登行
1956年(昭和31) 第一次南極観測隊に参加
1963年(昭和38) 東大カラコルム遠征隊に参加、副隊長として指揮をとる
1976年(昭和51) 日本山岳会ナンダ・デヴィ遠征隊に総隊長として参画 (出発直前の健康診断の結果、参加を断念した)
1980年(昭和55) 日本山岳会珠穆朗瑪(チョモランマ)登山隊に参加。登山隊長として指揮をとる
【会 員】
成蹊学園踏高会
東京大学山の会
日本山岳会名誉会員

満席の中での映画会 山との出会い
私が、初めて山と出会ったのは、7歳の時 (大正10年・1921年) である。父が友人を訪問する旅に私を同行した。その友人は木曽御料林の管理責任者であった。森林鉄道に乗せてもらって、どこか山間部につれていかれた。そして、高く大きい檜の木立の間から、雲をまとった、雨上がりの木曽御岳の姿を見た。とても美しかったことを、ほんとうにかすかに覚えている。これが都会育ちの少年であった私の心に、山が入ってきた最初であった。 大正13 (1924) 年、成蹊学園小学校2年生の夏、父に連れられて富士山に登った。吉田口から登り、5合目小屋で1泊し、御殿場口に下山した。80年後の今日、かすかに覚えているのは、すっかり日が落ちて暗くなった道を、父と子がトボトボと歩いている光景である。これが、登山という行為を経験した最初であり、その山は、たまたま日本列島で一番高い富士山だった。
今なお健在な「虹芝寮」
私が成蹊学園在学中に学制が変わり、新制の7年生高校が設置された。その結果、同じ学園で14年間を過ごし、移転は大学だけという恵まれた状況で学徒生活を送ることになった。この事実は、「山」と緑のある生涯を送ったことにおおいに関与しているように思う。 成蹊学園在学の昭和6 (1931) 年、山仲間の間で 「山小舎が欲しい!」 という望みがでて、上越国境の谷川岳の東側に適地を探し、山小舎を建築することになった。それが70年後の今日まで同じ場所に健在な 「虹芝寮」 である。この山小舎の適地探しや、小舎作りに関する諸々の手続き、そしてでき上がった小舎での生活や保全の仕事など……。いずれも、それまでやってきた単なる登山とは違う思いと目で山を見て、そして考えていかねばならないという、側面との付き合いがあった。母校の校長の・「金は出してやるが口は出さない」 というひと言が、我々青少年をひどく苦しめたが、実にすばらしい教育であり、非常に面白い経験だったと、今になって思い浮かべるのである。 しかし、山小舎を維持することの方がはるかに困難であり、ひとつの小舎を今日まで維持してきた成蹊大学の山好きの後輩たちに、 心から感謝したいと思う。
スキー事始め
私の父は、秩父宮家ができた時から御用掛として宮家に奉仕していたので、殿下が初めてスキーをなさった時 (大正11年・1922年)、細川護立さんの赤倉の別荘地にお供をした。その時にスキーを初めて経験した父は、なかなか面白いものだということで、直ちに私にスキーを買ってやろうと言った。そして探したが、子供用のスキーはどこにも売ってなかった。それで、作ることになったが、どうせだんだん大きくなるだろうといって、いくら手を伸ばしても先がつかめないぐらい大きなスキーと靴を作らせたのだった。そして、それを持って五色にお供をさせられたのである。初めて見る真っ白な吾妻の山は美しいと思ったが、スキーの履き方だけを教わって、鉢森山の麓でこ一行の下山をじ-つと待っていた辛く苦しい思い出は今も忘れられない。
自然から……「自力で学びとる」
私は山とスキーの存在を父から教わったが、どうして山に登るのか、どうしてスキーで滑れるのかということは全く教わらなかった。父は、同時に始めた私に教える腕前を持っていなかったのである。それで、山やスキーについて、自分で自然から学びとらなければならなかった。そして、一言居士流に言えば、自然から教わるのが最も自然で正当であると妄信していた。大学では、新しい仲間と一緒に山に登りスキーもしたが、少しも引けをとらないと自負していた。小さい頃から山やスキーを始め、自力で、山と、雪と、風から学び、それに対応してきた。そのことが今思えば、得意だった気がする。しかし、その仲間たちが 「世の中」 について、私の知らないことをいっぱい知っているのには仰天した。私は 「山」 しか知らない都会の坊ちゃんだったらしい。
登山の屁理屈
山登りには理屈がつきものであるということを、山の本で読んだ。本には 「山を想う」 という記事が多く、その方法論は、経済学や社会学で学んだように、静態的な均衡状態を山と人間との間に設定していた。山をこのように考えているのだ、こんないい山があるのだという話はあるが、学ぼうとしている技術については、十分な言葉で書いていないと感じた。なぜかと考えたとき、山登りの技術とは、「技術」と「作法」、つまり 「技法」 ではないかと思うようになった。この両方をわきまえなければ、正しい登山はできないのではないかと…。 ところが、作法というのは全部人間が作ったものであって、山が作った作法はない。山登りとはそんなものだったろうかと考えた。そしたら、問題にぶちあたった。今まで私のやってきた山登りは、どうだったのだろうかと……。 成蹊学園時代 (昭和8年・1933年) に高木君と谷川に登ったのは、当時ドイツの学生だったシュミット兄弟がマッターホルンの北壁を初登頂した直後だった。その記事が雑誌に載っていた。その真似をやっただけで、決して大したことじやない。非常に純朴なる学生であったともいえるが、流行の先端を真似て、岩登りをやったのではなかったかと…。
二つの「知」の併存
成蹊学園在学の15歳の春休みに、後立山の五竜と白馬を雪のある間に登ろうという話になった。高木君と2人で細野部落の大谷定雄という人夫を雇い、唐松の小屋に入った。その時、大谷が剣の方を眺めて 「剣にあの雲ができたら、2時間後に後立山は猛吹雪になる。吹雪が来る前に五竜へ行きましょう」 と言った。その時、唐松の周辺にはまだ青空が見えていたが、確かに黒部川の谷間を越えた剣には雲がかかっていた。慌ててピッケルとアイゼンを持ち、半分駆け足で五竜を往復し、帰途は牛首の辺りで体が舞いそうな猛吹雪にあったが、無事に小屋に戻った。あの時大谷が、2時間後の後立山の猛吹雪を予見できたのは、麓で農耕をしていた農民こその知識ではないかと思う。彼らは、白馬の麓で米を作って生きていたから、自然を肌で感じる知り方をしていたように思う。一方の知識は、学校や本で学ぶものだが、どちらの知り方も正しいのだと思う。知識には、自然から教わるものと、人から教わるものとの両方があるようだ。遊びや、余技としての山やスキーでは、人から教わるのではなくて自然から教わる、自然にそうなってきたように思われる。
「雪線」へのこだわり
戦前に私が盛んに登っていた日本列島の山々は、所詮、雪線のない山であった。だが、山登りの本の主役は、雪線以上の山や氷河のあるスイスの山々であった。雪線以下の山しかない国に住む私は、雪線以上の岩や氷の世界の山登りを求めていたのかもしれない。今日、外国の山で雪線の上下など考える人はいないと思う。しかし、我々の時代、山登りをする者にとっては、なかなか重要な問題であった。山々の状態が違うだけでなく、生活する人々の生態にも大きな相違があろう。極地の雪線は海の中にある。カラコルムもチョモランマも雪線を越える領域の登山であった。雪線を越えると氷河がある。その氷河の上にまた岩があり、氷河の固い雪と、それから岩と、両方を登ったり下りたりしなければならない。
それがヒマラヤの山登りだ。ところが、日本には雪線以上の山はないから、やったことがない。その雪線を解決するのは、お金のようで、どうもその辺りで昔と今の登山が違いだしたと感じている。
「集団的自由」の存在
それまで私がやってきた山登りとは、自由なスポーツであると思ってきた。その自由とは勝手気儘というものではなく、その山のある場所の掟を守るというものである。そして 「どこの山に、どのように登るか」 を決める自由は個人にあると思っていた。南極やヒマラヤの遠征では 「隊」 を形成して国から出て行く。そこには個人の自由は存在しないものと了解していた。ところが、3つの海外遠征で「集団の自由」 を体験した。その典型が南極観測隊であった。多くの人々が集まり、力を出しきって基地を拓き建設し、越冬した。この事実に接し、「集団の自由」と「個人の自由」 の存在と、その必要性を痛感した。
「登山考」と「責任の認識」
「山登り」 はスタティック (静態的) ではなく、山も動いているし、登る人間の方も動いている。だからむしろダイナミック (動態的)な関係にあって、それがちょうど釣り合っている時に安全な山登りができて、壊れた時に遭難をする。この関係を 「あいだがら」 と表現し、私の登山考としてきた。同時に、登山は本人の責任の問題であり、他人が責任を負うべきものではないと思っている。自分の遭難をリーダーのせいにするようなことは、もっとも山登りを知らない人のいうセリフである。しかし昨今の状況をみると、リーダーや添乗員が悪いといって、裁判沙汰になるということが日本以外でも起こっている。山登りの責任者というのは一体誰なのかという問題になり、登山における責任の認識が必要になってくる。他のスポーツでも同じようなことはあるかもしれない。日本山岳会は幸いにして、今まで大きな問題はおきていない。しかし、今後はこの問題に対しての考え方というものをだし、触れることが必要で、それが世の中のためにもなるのではないかと思っている。
今、思うこと
登山やスキーのできない年齢になった今、思うことがある。それは白馬や穂高の山案内人たちが、自然から肌で感じ知ったその知識を無にしてはいけないということである。それは説明することができない「知」 である。だからこそ、その「知」 に接し、経験することのない人たちに、何とかして伝え残すことが大きな課題であると思う。もし、科学だけが正しくて、科学以外のものは正しくないという雰囲気が日本山岳会の中にあるとすれば、それはいかがなものか。自然の移り変わり、その物語っているものを肌で感じ取らなければ生きていけないのである。その知識を、余技の中にどのように取り入れ、役立てていくかで、山での危険が少なくなるのではないかと、90歳になろうとする今、やっと気がついたところである。
【平成16年4月3日、東京体育館 (参加者120名) で行われた講演会記録を元に編集】(奈良 千佐子)

講演終了後の笑み。ご苦労様でした。

